




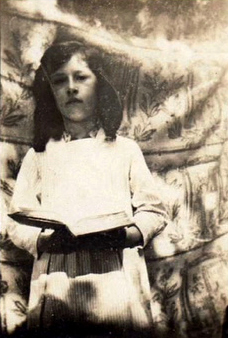  

1909年(0歳)
2月3日、パリに生まれる。
父は医師のベルナール・ヴェイユ。3歳上の兄に世界的な数学者のアンドレ・ヴェイユがいる。
家庭は裕福で、教育にも熱心だった。
1910年(1歳)
重病を患い、約11ヶ月間の闘病。これ以来、生涯にわたって虚弱体質に苦しむ。
1915年(6歳)
すでにこの頃から抜きんでた才能と知性を示すようになり、四行詩などを創作して家族を驚かせた。
1919年(10歳)
パリのフェヌロン高等中学校に入学。
成績は非常に優秀だったが、健康上の理由で欠席が多かった。
1921年(12歳)
パスカルの「パンセ」を愛読。この頃からギリシャ語を学び始める。
1923年(14歳)
自らの能力の凡庸さに真剣に悩み、自殺することを考えるが、
数ヶ月の苦しみのあと「真理を欲し、真理に到達すべくたえず注意を込めて努力するならば、
誰でも真理に達することができる」という確信をもつようになる。
1924年(15歳)
ヴィクトル・デュリュイ高等中学校哲学科に入学。
生涯にわたって苦しむこととなる神経性頭痛がこの頃から始まる。
1925年(16歳)
大学入学資格試験(哲学科)に合格。
高等師範学校の入学準備のためアンリ四世高等学校に入学。
このアンリ四世高で哲学者アランと出会い、多くの指導を受ける。
1927年(18歳)
友人らが始めた「民衆大学」の運動に参加し、鉄道労働者に対して無報酬で講義を行った。
1928年(19歳)
10月、高等師範学校に入学。同級生28名のうち女性は3名。
高等師範学校に入学後も、アランの講義へは引き続き出席し続けた。
この頃から様々な社会活動、学生運動に参加。
すでにこの頃から平和主義者としてのヴェイユの名は学内でも有名だった。
1930年(21歳)
持病の頭痛の強烈な発作を初めて発症。
高等師範学校卒業。卒業論文「デカルトにおける科学と知覚」。
1931年(22歳)
ロマン・ロランやサルトルらと共に、知識人の徴兵制反対の声明文に名を連ねる。
高等師範学校を終え、大学教授資格試験に合格。受験者107名のうち合格者は11名。
同年秋より哲学教授としてル・ピュイ女子高等中学校に勤務。
ル・ピュイにおいては、生徒たちに自分でものを考えることの重要さを説き、
学校のカリキュラムを無視して独自の教育法を取り入れた。
そのため彼女の生徒たちは大学入学試験では良い成績を挙げることはできなかったが、
終生にわたってヴェイユのことを慕うようになる。
教職をする傍ら、ル・ピュイの労働者や失業者を支援するため労働組合活動に積極的に参加。
労働者学校にも協力。サンティエンヌの炭坑夫のために講座を行う。
また、労働組合の新聞や前衛的な雑誌に多くの論文を発表した。
1932年(23歳)
ル・ピュイの労働者や失業者のために過激な活動を続けたため、市警察に一時逮捕される。
教育委員会に転勤を命ぜられたりもしたが、ヴェイユはこれを拒絶した。
この後も各紙に労働関係の論文を多数発表。失業者の大規模なデモにも参加。
夏にドイツ旅行。
秋にオセール女子高等学校に転任。
オセールにおいても労働者たちと好んで接触し、また生徒たちには独自の教育を貫いた。
このため周囲の評判は「変わり者」であった。
この年の冬、ドイツ共産党とスターリンのソビエト連邦を非難する論文を次々と発表。
1933年(24歳)
ロアンヌ女子高等中学校に転任。
ここでも彼女は周囲から「正体不明の神秘的存在」として映る。
ロアンヌで行った講義はのちに生徒たちの手によって出版された。(ヴェーユの哲学講義)
サン・ティエンヌの労働者を支援するため、再び過激な労働組合活動に参加。
論文「自由と社会的抑圧の諸原因についての考察」「われわれはプロレタリア革命に向かっているのか」を発表。
1934年(25歳)
自分の体で辛い現実の生活と接触したいという強い思いから、電機工場へ入社し女子工員として働く。
その後もカルノー鉄工所、ルノー自動車工場など、同年7月まで工場での仕事を転々とし、<
これらの工場における労働者の不幸と苦しみを自ら体験し日記につづった。(工場日記)
1935年(26歳)
8月にポルトガルへ旅行。ポルトガルの小さな漁村で一夜を過ごしたとき、
「キリスト教は優れて奴隷の宗教である」という啓示を受ける。
秋にブールジュ女子高等中学校へ赴任。
1936年(27歳)
これまで以上に頭痛と疲労に苦しむ。
7月にスペイン市民戦争が起こり、8月にバルセロナへ。
ここでドゥルティの無政府主義者たちと共に義勇軍兵士としてアラゴン戦線へ参加。
8月末に負傷のため戦線を離脱し入院。
この戦争で非人間的な所業を数多く見聞し、戦争の残虐さと集団悪を理解する。
12月、健康状態が悪化したため教職の休暇を延長。
1937年(28歳)
健康状態がさらに悪化。スイスのモンタナで静養。
この頃から外側の社会的活動からは身を引き、内面を深く探るようになる。
夏にイタリア旅行へ行き、聖フランチェスコの故郷アッシジの礼拝堂で宗教的体験をする。
この時、礼拝堂の中で生まれて初めてひざまずく。
秋からサン・カンタン高等中学校へ赴任するが、病気のため再び休暇を取る。
1938年(29歳)
年初から耐え難い頭痛に苦しめられる。多くの神経科の病院に訪れたが原因が分からなかった。
春、ソレム修道院に滞在し、すべての勤行に参加。
激しい頭痛に苦しみながら典礼に臨むうちに「キリストの受難」の意味を決定的に悟る。
同じソレムで英国の形而上派詩人たちの詩に出会い、感銘を受ける。
とりわけジョージ・ハーバートの詩「愛」を愛唱するようになる。
頭痛の激しい発作の中でこの詩を読み「キリストが降下し、とらえられた」という神秘体験をする。
1939年(30歳)
休職を延長。
この時期、インドの「バガヴァバッド・ギーター」や、「イリアス」などのギリシアの古典を愛読。
「イリアスまたは力の詩篇」「ヒトラー主義の起源に関する考察」なども執筆。
9月、第二次世界大戦が勃発。
1940年(31歳)
6月、パリ陥落のためパリを離れ南フランスのヴィシーへ。
この地で戯曲「救われたヴェネチア」の執筆に没頭する。
10月、マルセイユに移る。
1941年(32歳)
ウパニシャッドなどのインド哲学の研究に没頭する。
6月、J.M.ペラン神父と出会う。ペラン神父との出会いは彼女に深い霊的感化を与えた。
8月、かねてからの希望であった農民生活を送るため、
ペラン神父の紹介でサン・マルセルに住む農民哲学者ギュスターヴ・ティボンの元を訪れ、
ティボン家の畑仕事や近隣の村の葡萄摘みなどの労働に従事。
この間、潰れかけの古びた百姓家で寝泊まりし、食事はときに野イチゴだけで済ませることもあった。
労働の傍らティボンと共に毎日祈り、読書をし、論議をして友情を育んだ。
サン・マルセル滞在中に、のちに「カイエ」として出版されるノートのほとんどをティボンに渡す。
1942年(33歳)
4月の復活節にカルカソンヌへ旅行。詩人ジョー・ブスケと出会う。
ジョー・ブスケは戦争で半身不随となりカルカソンヌで療養していた。
その彼のもとへシモーヌ・ヴェイユが訪れ、寝台のかたわらで朝まで語り合って友情を深めた。
その後、ヴェイユはブスケに対して何通かの手紙を送る。(カルカソンヌの一夜)
5月、ドイツ軍によるフランス全土占領の危機が迫り、両親と共にアメリカへ亡命することになる。
亡命のためマルセイユを出発する際、ティボンに別れの手紙や数冊のノートを渡す。
ペラン神父には「精神的自叙伝」等が書かれた重要な手紙や論文を5月までにいくつも送っている。
3週間ほどカサブランカに滞在したのち、6月末にニューヨークに到着。
しかし祖国を思う気持ちは抗しがたく、11月にはロンドンに移り、自由フランス政府のもとで働く。
1943年(34歳)
自由フランス政府の要望で、のちに「根をもつこと」として出版されることになる報告書を書く。
ロンドンに来てからは夜を徹して様々な論考を書き続けた。
こうした中、ヴェイユは戦時下の食糧不足や同胞の困窮した生活を思い、ほとんど食事をとらなかった。
頭痛、疲労、栄養失調によって体調がさらに悪化、衰弱する。
4月、下宿の部屋で倒れ、意識不明の状態で病院に運ばれる。急性肺結核の診断。
療養中も食事を取ることを拒絶し、衰弱が進む。
8月、ケント州アシュフォードのサナトリウムの病院に移される。
一週間後の8月24日の夜に死去。享年34歳。
死因は「飢餓および肺結核による心筋縮退から生じた心臓衰弱」。
死亡診断書には次のように書かれていた。
「患者は精神錯乱をきたし食物を拒否、みずから生命を絶った」。
8月30日、アシュフォードの墓地に埋葬される。

引用・参考文献
「シモーヌ・ヴェイユ」 田辺保 / 講談社現代新書
「重力と恩寵」 田辺保 訳 / ちくま学芸文庫
「前キリスト教的直観」 今村純子 訳 / 法政大学出版局
「シモーヌ・ヴェーユ著作集〈5〉根をもつこと」 山崎庸一郎 訳 / 春秋社

|