



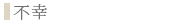
何ごとが起ころうとも、不幸が大きすぎるなどと思うことがあろうか。
なぜなら、不幸に烈しく襲われ、不幸のために屈従を強いられてこそ、人間の悲惨を知ることができるのだから。
それを知ることこそが、あらゆる知恵への門なのであるから。
-
この世の不幸がなかったならば、私たちは天国にいると信じるかもしれないだろう。
-
地獄についての二つの考え方。
普通の考え方(慰めのない苦しみ)。
私の考え方(にせの完全な幸福。あやまって天国にいると信じること)。
-
できるかぎり不幸を避けようとつとめなければならない。
自分の出会う不幸が、完全に純粋で、完全につらく苦しいものであるために。
-
不幸は、とてもあるはずがないと思い込んでいるものを、無理にも現実として認めるようにさせる。
-
不幸。
時間が、考える存在としての人間を、どうしようもなく、とうてい耐え切れるはずのないもの、
しかも必ずやってくるもののほうへと連れ去って行くこと。
流れていく毎秒毎秒が、この世にいるひとりの人間を、何かしら耐え切れないもののほうへと引きずっていく。
-
不幸がこのまま続いていくことも、不幸から解き放たれることも、
どちらももう耐え切れなくなるような一点が、不幸にはある。
-
生き地獄といっていい不幸の中には、完全の状態と同じように、なにかしら個々の人間を離れたものがある。
-
自分が不幸なとき、じっと不幸を見つめられる力をもつには、超自然的なパンが必要である。
-
極限の不幸にもとづく苦しみは、<わたし>が外部から滅ぼされることである。
-
まったく執着から離れきるためには、単なる不幸だけでは十分ではない。慰めのない不幸が必要である。
慰めがあってはならない。これといってかたちに表せるような慰めが少しでもあってはならない。
そのとき、言葉に言いつくせぬ慰めが、降り下ってくる。
(重力と恩寵)
不幸におけるあらゆる慰めは愛と真理を遠ざける。
これぞ神秘のなかの神秘である。この神秘に触れるなら安心してよい。
願望や嫌悪または快楽や苦痛を、自分のなかで変質または抹殺しようとしてはならない。
それらを色彩感覚と同じく、色彩感覚に対する以上の信頼をよせることなく、受動的に感受せねばならない。
私の窓ガラスが赤ければ、一年中昼も夜も合理的であろうと努めても、部屋がばら色に染まるのを見ずにはいられない。
また、部屋がこのように見えるのは必然であり正しく善いことだと知っている。
同時に、情報としての部屋の色調に限定的な信頼をおくにとどめる。窓ガラスとの関連性を知っているからだ。
私のなかに生じる願望や嫌悪または快楽や苦痛を、いかなる種類にせよ、このように甘受すべきであって、
これ以外のかたちで受容してはならない。
もっぱら無差別的に必然に由来するかぎり、それらはすべて神に由来する。それ意外はありえない。
(カイエ3)
真の不幸の外的な形はほとんど常に悪いものなのです。それを隠そうとすると嘘をつくことになります。
神のご慈愛が輝いているのは不幸そのものの中です。その奥底、慰めることのできない苦しみの中心なのです。
魂が「神よ、あなたはなぜ私を捨てられたのですか。」という叫びを、
もはや押さえきれなくなる状態まであくまで愛を貫き通して倒れるならば、あるいは、
そのような状態でも愛することを止めないならば、もはや不幸でもなく喜びでもない、中心的な、本質的な、純粋な、
眼には見えない、喜びにも苦しみにも共通の本質、神の愛ですらある何ものかについに触れるのです。
それゆえ、喜びとは神の愛との接触の快さであり、不幸とはこの同じ接触が痛ましい時の傷であり、
この接触それ自体だけが大切であってその形式は問題ではない、ということを知っています。
同じように、久しく会わずに、非常に親しい人に再開する場合、その人と交わす言葉が大切なのではなくて、
ただその人の存在を我々に確認させてくれる声の音色だけが重要なのです。
このような神の臨在の認識は、不幸の恐ろしい苦しみを慰めもしなければ、
不幸から何かを取り除いてくれるわけでもありませんし、引き裂かれた魂を癒してくれるものでもありません。
しかし、我々に対する神の愛は、その苦しみ、そのずたずたに引き裂かれたものの実体ですらあるということを、私は確かに知っております。
(神を待ちのぞむ)
苦しみの領域において、不幸はなにか特別なものであり、特殊なものであり、削減できないものである。
不幸は単なる苦しみとは、まったく別のものである。
不幸は、魂をすっかりとらえつくし、魂の奥深くまで、不幸だけに属するしるし、奴隷のしるしを刻みつける。
-
不幸は、肉体的な苦しみと切れ離せないものであるが、やはりそれとはまったく別のものである。
-
愛する人がいなくなったり、死んだりする場合においても、
苦悩の中で取り去ることのできない部分には、どこかしら肉体的な苦痛に似たものがある。
呼吸困難、心臓のまわりが締めつけられるような感じ、どうしようもない渇き、飢餓感、
そのときまで束縛されてきちんと方向づけられていたエネルギーが突然解放され、方向を見失ったための、
生物学的ともいえる錯乱状態に似たものがある。
苦悩は、取り去ることのできないこういう核のまわりに集約されていないならば、
結局ロマンチックなもの、文学的なものにすぎないのである。
屈従の状態もまた、体全体の劇的な状態であって、恥ずかしめを受けて、体はそれを跳ね返そうとしているのだが、
力の不足が、恐怖のために、仕方なくじっとこらえていなければならない姿である。
ところが一方、単に肉体的な苦痛だけならそれはたいしたことではなく、魂の中にどんな痕跡も残さない。
歯痛はその一例である。一本の歯が腐って、そのために何時間か激しい痛みが起こっても、
いったん過ぎ去ってしまえば、それはもう何でもないものになってしまう。
肉体的な苦しみでも非常に長いあいだ続いて、ひっきりなしに起こるものの場合は、また別である。
けれどもそういう苦しみは、単なる苦しみとはまったく違った性質のものであることが多い。
それは不幸になることが多い。
-
不幸は、人生を根絶やしにするものであり、多少弱められているといっても、いわば死に相等しいものであり、
肉体的な苦痛を伴って襲いかかったり、または、肉体的な苦痛の接近を不安がらせたりして、
否応なく魂の目の前に立ちはだかるのである。
肉体的な苦痛がまったくなかったとしたら、魂は不幸を感じることはない。
なぜなら、人間の思考は、いつも何らかの具体的な対象に向かうものだからである。
動物が死を恐れて逃げるように、思考も同じように早く、抑えようとしても抑えきれぬぐらいに、不幸を避けて逃れる。
この世においては、思考を引きずっていく特別な力のあるものは、肉体的な苦痛だけであり、そのほかには何もない。
もちろん、今ここで一々述べることはできないが、ある種の身体的な現象も、肉体的な苦痛と厳密に相通じるものであって、
当然、同じものとしてみなしておかねばならない。
肉体的な苦痛に対する恐れといったようなものは、とりわけてこういう種類のものである。
-
本当に不幸が存在するといえるのは、人生を引っつかみ、根絶やしにするような出来事が起こって、
直接にか間接にか、とにかく社会的、心理的、肉体的に、その人生のありとあらゆる部分を痛めつける場合だけである。
社会的な要素は何よりも重要である。本当に不幸が存在する場合には、必ず、どんな形にもせよ、
社会的な失墜、または、そういう失墜の不安を伴うものである。
不幸と、それから、どんなにすさまじく、どんなに深く、どんなに永続的なものであっても、
固有の意味の不幸とは違う別なすべての苦悩とのあいだには、
連続したところと、同時に、一つの敷居で区切られたところとがある。いわば、水の沸騰点みたいなものである。
ある限界点があって、それを超えた向こう側には不幸が存在し、こちら側には存在しない。
この限界点を、純粋に客観的に求めることはできない。個人的なあるゆる種類の要素を考慮に入れなくてはならない。
同じ一つの出来事でも、ある人をたちまち不幸の中に突き落とすかと思えば、別の人に対してはそうでないことがある。
-
人生の大きい謎は、苦しみではなく、不幸である。
罪もない人々が殺され、拷問を受け、国を追われ、窮乏や隷属の状態に突き落とされ、
収容所や牢獄に幽閉されることがあるのは驚くにあたらない。そういう行動を起こす罪人がいるのだからである。
また、病気のために、生命の機能を麻痺させ、
生けるしかばねのようにする長い苦痛を耐え忍ばねばならないことがあるのも驚くべきことではない。
この自然は、機械的な必然性の盲目的なたわむれのままにゆだねられているのだからである。
しかし、神が不幸に対して、罪なき人々の魂そのものをとらえつくし、
絶対君主のように魂を奪い去る力を与えておられることは、驚いていいことである。
どんなにうまくいった場合でも、不幸の刻印を受けた人は、魂の半分だけしか保っていられないのである。
たまたま不幸の攻撃に襲われ、
半分つぶされた虫のように、地面の上でもがき苦しんでいるよりほかに仕方のない人々にとっては、
自分たちの身に起こった事柄を言い表わすに足る言葉はありえない。
まわりで出会う人たちの中でも、どんなに苦しんだことがあろうと固有の意味の不幸と触れ合ったことが一度もない人は、
彼の不幸がどんなものかにまったく思い及ぶことができない。
それは、何かしら特別なものであり、他のものに還元することができないものである。
いわば、つんぼで、おしの者に対しては、音がどんなものであるかを到底考えつかせることができないようなものである。
-
不幸のために、しばらくの間、神が隠れて見えないことがある。
死者の不在よりも、もっと不在であり、真の暗闇である土牢の中の光よりも、もっと暗くて見えないことがある。
魂全体が、何がぞっとするような恐ろしさの中にひたされている。
-
不幸は、人を頑なにし、絶望させる。
不幸は魂の奥深くに、灼熱した鉄で烙印を押すように、
自己自身への蔑みと、嫌悪と、反発と、罪悪感と、汚辱感とを刻みつけるからである。
そういうものは、もともと罪によって当然生じてくるはずのものであるが、実際は、罪によっては起こってこない。
罪は罪人の魂に宿っておりながら、一向に気づかれずにいる。
罪のない人の魂も、不幸なときには、悪の存在を自分のうちに感じとる。
まるで、本来なら罪人の場合にこそふさわしい魂の状態が、
罪と切り離され、不幸と結びついたかのように、何もかもそうなってくるのである。
つまり、不幸な人は、罪がなくてもそうなるようになってきているのである。
-
不幸は何よりも名前を持たないもの(アノニム)であり、人々をとらえて人格を剥ぎ取り、"もの"にしてしまうのである。
不幸は無関心であり、無関心なものの冷たさ、金属的な冷たさであり、
いったん不幸にさらされると、人々の魂は底まで凍ってしまうのである。
その人々は、もはや二度と決して、あたたかさを取り戻すことはありえないであろう。
もはや二度と決して、自分たちも人間のはしくれなのだと思おうとはしないであろう。
-
金づちで釘を打つとき、釘の頭の広い部分が金づちの衝撃を受け、その衝撃がそのまますっかり釘の先端に伝えられる。
釘の先端が単に一つの点ほどの広さしかなかったとしても、衝撃は何一つ失われずに伝えられる。
もし今、金づちと釘の頭が無限に広いものであったとしても、起こることはすべてまったく同じである。
釘の先端は、この無限な衝撃を、先端の接触している一点に伝えていくはずである。
極端な不幸というものは、肉体的な苦痛でもあり、
また、魂の懊悩、社会的な失墜でもあるのだが、いわば、この釘みたいなものである。
その先端が、まさに魂の中心に触れている。
釘の頭は、空間と時間の全体にわたって広がった全必然性である。
不幸は、神の驚くべき技術の妙である。
それは簡単ではあるが、巧妙な一つの装置であって、
有限な被造物の魂の中に、この盲目的な、荒々しい、冷酷な、無限の力を打ちこんでくるのである。
神と被造物とのあいだを隔てる無限の距離全体が、まったく一点に集中して、魂の中心に穴をうがったのである。
このような事態が起こっても、人間はこの作業になんら関わるところがない。
人間は、生きながらアルバムの上にピンでとめられた蝶のようにもがく。
しかし、こういう恐ろしさの中でも、なおも人間は愛しようと願い続けることができる。
このことには、どんな不可能性もなく、どんな障害もない。どんな困難もないと言ってもいいぐらいである。
いったい、苦痛がどんなに激しくても、そのために、失神してしまうほどでないかぎりは、
正しい方向へと向かおうと願う魂のこの一点を損なうことはないからである。
釘が打ちこまれていても、じっと神のほうへと向けられた魂を持っている人は、
いわば、世界の中心に釘づけられているのである。
それこそ、真の中心であって、単なる真中ではなく、空間と時間の外側にあり、神そのものである。
空間にも属さない次元、時間でもない次元、まったく違った次元に基づいて、
この釘は、全被造物を超え、神と魂を分かつ厚い"とばり"をつらぬいて、穴をうがったのである。
この驚嘆すべき次元のゆえに、魂は、自らがつながれている体の今ある場所と時間とを離れ去ることなしに、
空間と時間の全体を超え、神の存在の御前に、いたり着くことができるのである。
魂は、全被造物と創造者とが交わる点へと到達する。
この交わる点こそ、十字架の横木が交差する点である。
(神を待ちのぞむ)


|