



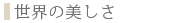
ただ一つ、真に美しいもの、神が真にご臨在したもう唯一の美しさ、それは宇宙の美しさである。
宇宙よりも小さいもので、美しいものは何もない。
宇宙の美しさはどのようなものかと言うと、たとえば、
完全な芸術作品と称するにたる作品があったとすると、そういう作品の美しさに似ている。
だから、宇宙には、終極的な目標、ないし、なんらかの善となりうるようなものは、何一つ含まれていない。
宇宙は、普遍的(宇宙的)な美しさのほかには、どんな究極性をも含んでいない。
宇宙が究極性というものを完全に欠いているという点こそ、
宇宙に関してぜひとも知っておかねばならない大切な真理である。
究極的な関係を宇宙に適用することはできない。そんなことをすれば、虚偽になるか、誤謬におちいる。
-
美しさこそ、この世において、唯一の究極的なものである。
それはどんな終わりもない究極性なのである。
美しいものは、それ自体のほかに、どんな善も持たない。
それが私たちに顕れるままに、その全体において、そうなのである。
私たちは、美しいもののほうへと、何を求めているのかも知らずに、向かう。
美しいものは、その存在自体を私たちに与えてくれるのである。
私たちは、それ以外のものは何も望まず、それをしっかりと持ち、しかもなお望み続ける。
それが何であるかは、全然わからない。
美しさのあとを追いかけたいと思うのだが、それはただうわつらだけにしかない。
美しさは、いわば鏡みたいなもので、目指す宝物から私たちの願いを突き返してくるのだ。
美しさは、スフィンクスであり、謎であり、神秘であって、苦しいほどいらいらさせる。
私たちは、それを食べて養分にしたいと思う。
しかし、美しさは、目で見られるものにすぎず、一定の距離においてしか現れない。
人間の生活の中で一番痛ましいことは、見ることと食べることが二つの違った働きだということである。
ただ、天のかなた、神の住みたもう国においてだけ、この二つが同じ一つの働きとなるであろう。
-
美は、それ自体のうちにどんな目標も含んでいないものであるから、この地上において、ただ一つの究極的なものとなる。
つまり、地上には、目標などというものは、少しもないのである。
私たちが目標だと思っているものもすべて、手段にすぎない。これは明らかな真理である。
お金は、物を買うための手段てあり、権力は、命令を下す手段である。
私たちが、財宝と言っているものはみな同じであって、その点が明白に現れているかいないかに多少の差があるにすぎない。
美だけが、ほかのものの手段ではない。
美だけが、それ自体においてよいものである。
たとえ、美の中にはどんな財宝もないように見えようとも。
美は、それ自体、一つの約束であって、財宝ではないように思われる。
つまり、美は、自分自身を与えるのであって、ほかのものを与えることはない。
しかも、美はただ一つの究極的なものであって、人間のはたすあらゆる努力の中に存在している。
もちろん、あらゆる努力は、ただ手段だけを追い求めている。
この世に存在するものはことごとく、手段にすぎないからである。
しかし、美は、その努力を、究極性で色どり、みごとな開花を遂げさせるのである。
もしそうでなかったとしたら、人間は、その努力のうちに情熱を感じることもなく、
したがって、エネルギーを傾けることもありえないであろう。
-
世界の美しさは、全被造物に対する神の知恵の協力である。
「ゼウスがすべてのものを完成し、バッカスがさらにその仕上げをした」と、オルフェウス派の詩の一つにある。
この仕上げこそ、美の創造である。
神は、宇宙を創造されたが、私たちの長兄である神の御子が、私たちのために、美を創造してくださった。
世界の美しさは、物質を通して、私たちに微笑みかけたもう神の慈しみの顕れである。
神は、宇宙的な美しさの中にこそ、まさしく臨在したもう。
この美しさへの愛は、私たちの魂の中にくだって来られた神から出て、宇宙に臨在される神のほうへと向かう。
ここにもまた、何かしら秘跡的なところがある。
宇宙的な美しさについては、まさにこのとおりである。
しかし、今、神は別として、宇宙全体が、それ自体だけで美しいと言っても、その言葉は不適切ではない。
宇宙の中にあるすべてのもの、宇宙よりも小さなものも、美しいと言ってもよい。
美しいというこの語の厳密な意味から少し広げて用い、
ただ間接的に美と関わっているもの、単に美の模倣にすぎないものにも適用することができる。
こういう二義的な美もすべて、宇宙的な美しさに導くものとして、無限の価値を持っている。
-
究極的なものがなく、とくに意図がないということこそ、世界の美しさの本質であるから、キリストは私たちに対して、
雨や太陽の光が正しい者の上にも悪人の上にも区別なしにそそがれるさまを見よと命じられたのである。
このことはまた、プロメテウスの崇高な叫びをも想い起こさせる。
「すべての人のために、同じ一つの光があり、天の定めによって回転する。」
キリストは、こういう美しさに学ぶようにと、私たちに説いておられるのである。
プラトンもまた、『ティマイオス』篇の中で、じっと思いをこらすことにより、
私たちがこの世の美しさと相似た者となるように、また、昼、夜、月、季節、年を次々と生起させ、
循環させる回転運動の調和に相似た者となるように、すすめている。
こういう回転運動においても、その全体の仕組みの中には、特別な意図や究極性がないことは明白である。
そこには、純粋な美しさが輝いている。
-
いろいろなもの、存在物、出来事などが、ふさわしくあるということはどういうことであろうか。
それらが存在するということであり、
それらが存在しないこと、それらがそのようでないことを私たちが望まないということに尽きる。
もしそんなことを望むとしたら、それは、私たちの普遍的な祖国に対する背信であり、宇宙へのストア派的な愛の欠如である。
私たちは、事実において、そういう愛が可能なようにつくられている。
この可能性が、世界への美しさと呼ばれるのである。
ボーマルシェは、
「どうして、これこれでなければならないのだ。ほかのものであってはいけないのか」と問うたが、
この疑問にはついに答えが与えられることはない。なぜなら、宇宙には究極性が欠けているからである。
究極性がないということは、必然性が支配していることである。
物事はみな、原因があるが、目的がない。
-
世界の美しさは、物質がそれ自体もっている属性ではない。
それは、世界と私たちとの感受力との関係である。
その感受力は、私たちの体と、魂に依存している。
宇宙は美しいといっても、そこにはあらゆる段階があることを信じなければならない。
また、同じ考える存在でも、実際に存在するもの、単に可能的に存在するものを問わず、
それぞれの身体的、心的構造に応じて、宇宙は充実した美を示すと一般的に信じなければならない。
このように、無限に存在するさまざまな完全な美の調和によって、世界の美しさの超越的な性格が作られるのである。
しかしながら、こういう美しさについて、私たちに感じられるものは、人間の感受力に特に向けられたものだけである。
-
魂を導くものが愛であるとき、人は必然性をじっと見つめることにより、
いよいよその金属的な硬さと冷たさとを身にしみてじかに感じとり、そして一そう世界の美しさへと近づいていく。
ヨブが体験したことも、こういうことであった。
彼は、苦難のうちにあって、あくまでも誠実であったし、
その真実をゆがめるような考えを抱くようなことは断じてしなかったので、
神は彼のほうへと下って来られ、世界の美しさを彼に啓示してくださったのであった。
-
世界の美しさへの愛は、普遍的な愛であるが、その愛に従属する、二次的な愛として、
真に価値ある個々のすべてのものに対する愛をもおのずと誘い出してくる。
運命がまかり間違えば、破壊してしまうかもしれない個々のものに対する愛である。
そういう真に価値あるものは、世界の美しさへと向かう段階を形作り、そこに導く入口となるものである。
さらに進んで、ついには世界の美しさにまで達する人は、そういう個々のものに対しても、
愛を割引きすることなく、前よりもさらに大きい愛をそそぐようなる。
-
筋肉労働は、世界の美しさと触れ合う特別なあり方であるが、それが最もうまくいった場合には、
何かにこれに匹敵するものが見出せないくらいに完全な触れ合いとなることがある。
芸術家、学者、思想家、瞑想する人などは、非現実的な薄皮の覆いを通して宇宙の姿がありありと見えていなければならない。
その薄皮のために、宇宙は隠され、大ていの人々にとって、生涯のほとんど全時期を通して、
宇宙は、夢の世界か、劇の背景のように見えるのである。
芸術家などは光のように見えていなければならないのであるが、そのように見られない場合が多い。
一日の労働のために、つまり、一日中物質に従属して過ごしたために、体中がへとへとに疲れ切った人は、
いわば、その肉体に、宇宙の現実をとげのように抱いている。
そういう人にとって困難なことは、見つめることであり愛することである。
それができたら、現実にあるものを愛することができるようになる。
-
古代においては、世界の美しさへの愛は、人間の思考において、非常に大きい位置を占め、
人間の生活全体を、すばらしい詩で包んでいた。
シナにおいても、インドにおいても、ギリシアにおいても、どの国民においても同じだった。
ギリシアのストア哲学には、どこかしら驚嘆すべきところがあり、
原始キリスト教、とくに聖ヨハネの思想は、これにずいぶん近いものであるが、
何よりも世界の美しさへの愛がほとんどそのすべてであったと言ってもよい。
イスラエルの場合も、旧約聖書のいくつかの個所、詩編、ヨブ記、イザヤ書、智恵の書などのある部分には、
世界の美しさについて比類のない表現が含まれている。
キリスト教思想においても、世界の美しさがいかなる位置に占めうるかを、聖フランチェスコの例が明らかにしている。
彼の詩は、詩としても完全であったばかりでなく、彼の生涯全部が、いわば生きた完全な詩であった。
たとえば、彼が独りで心霊修業をするために、また、修道院を建設するためにどのような場所を選んでいるかということも、
それ自体もっとも美しい生きた詩であった。放浪も、貧乏も、彼においては詩となった。
世界の美しさとじかに触れ合うために、彼は自分を裸にしたのである。
-
今日、白人種は、ほとんど世界の美しさに対する感受力をなくしてしまったように思われる。
そればかりか、白人がその武器、その商業、その宗教をたずさえて行ったところでは、
どの大陸においてもまるで一生懸命にこういう感受力を消し去ろうと努めてきたようにみえる。
しかしながら、この現代において、白人の国では、
世界の美しさこそ、神を深く迎え入れることのできるほとんどただ一つの道なのである。
美の感情は、そこなわれ、ゆがめられ、汚されているとはいえ、
今もなお、人間の心の中に強い原動力として、じっとそのまま残っている。
世俗的な生活のさまざまな関心事の中に、生き続けている。
もしこの感情が真正な純粋なものとされたならば、世俗的な全生活をそのままことごとく、神のみもとへ運び去り、
信仰の完全な肉化(アンカルナシオン)を可能ならしめるものとなる。
さらに、一般的に言って、世界の美しさによるのが、誰にも可能な、一番やさしい、最も自然な道である。
どんな魂でも一旦、わが身を外に開くとき、神は魂の中へと急いで下って来てくださり、
魂を通して不幸な者を愛し、不幸な者に仕えられるのであるが、
同じようにまた、魂を通して、ご自身の全被造物の感覚的な美しさを愛し、賛美するためにも、
魂のところへ来てくださるのである。
しかも、反対もまたさらに真である。
美しいものを愛する魂の生まれながらの性向こそ、最も多く神が用いられるわなであって、
それによって、いと高きところの息吹きへと魂を解き放ちたもうのである。
-
魂は、世界の美しさと触れ合うことだけを求めており、より高度な段階では、神との触れ合いだけを求めている。
しかし、同時に魂は、この触れ合いを避けようとしている。
魂が何かを避けようとするのは、醜さの恐れとか、真に清らかなものとの接触を常に避けようとしているのである。
平俗なものはすべて、光を避けるからであり、どんな魂の中にも、
完全へと近づいた魂は別として、平俗な部分が大きく広がっている。
この部分は、ほんの少しでも、純粋な美とか純粋な善が現われると、そのたびごとに恐慌に襲われるのである。
この部分は、肉体の背後に隠れており、肉体を覆いにしている。
魂の平俗な部分も、小さい口実を設けて、光を避ける必要を覚える。
快楽の追求とか、苦痛の恐れとかが、その口実として役立つ。
そこにあるのもまた、快楽そのものではなく、魂を支配する絶対性である。
ただし、嫌悪の対象としてあるのであって、魅惑の対象としてあるのではない。
また、多くの場合に、肉の快楽の追求がなされる場合に二つの衝動が一緒になっている。
純粋な美を追い求めようとする衝動と、美から遠く逃れようとする衝動とがあって、
見分けのつかないような混乱の中に入り混じっている。
とにかく、どのようなものであっても、人間の行う営みにおいて、
世界への美しさへの配慮が見られないということは決してないのである。
もちろん、それを受けとめているイメージは、多少なり形が崩れていて、汚れているけれども。
したがって、人間の生活の中には、自然の領分に属するような領域は少しもない。
超自然的なものが、どこにも、隠された姿で存在しているのである。
-
世界の美しさは、迷宮の出口である。
-
美しさと何らかの関連があるものは、時の流転からまぬがれていなければならない。
美は、この地上においては永遠である。
-
世界の美しさとは、世界の秩序が愛されているということである。
-
世界の秩序、世界の美しさへの愛は、自己放棄から生じる。
神が創造において示される自己放棄に似た自己放棄からである。
世界の秩序への愛によって、私たちもまたその一部分をなすこの宇宙を創られた神の愛にならうのである。
-
芸術は、宇宙全体の無限の美しい姿を、人間が形作った有限量の素材のうちに移し植えようとするこころみである。
このこころみが成功すれば、片々たる素材が、宇宙を隠してしまうことはありえず、
むしろ逆に、宇宙の真実をその周辺にあらわし尽くすはずである。
世界の美しさを正しく、純粋に反映していず、
その美しさの上にじかに開かれた切り目でないような芸術作品は、美しくも何ともない。
そういう作品は、一級品ではない。
その作者には、多くの才能があるのかもしれないが、正しい意味で天分を持っていない。
最も有名な、最も賞賛されている芸術作品の中でも、大多数の場合はこのとおりである。
真の芸術家とは、世界の美しさと、実際に、じかに触れ合った人のことである。
その触れ合いには、どことなく秘跡的なところかせある。
一級の芸術作品は、すべてたとえその主題がどんなに世俗的なものであろうとも、神に霊感を与えられている。
それ以外の作品は、なんら神の霊感を受けていない。
そのかわり、他の作品の中には、ある種の美を覆い隠してしまうような「美」の輝きがあり、
それはおそらく悪魔的な光輝であろうと思われる。
(神を待ちのぞむ)


|